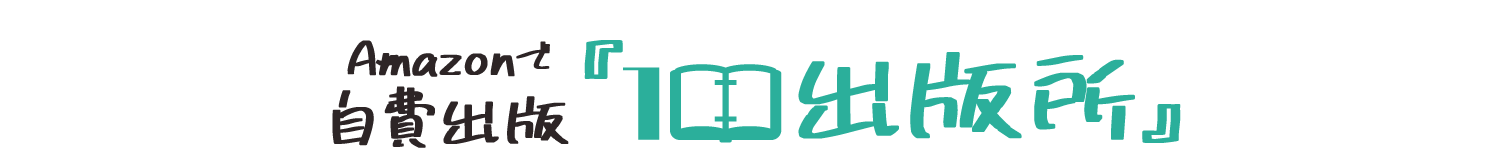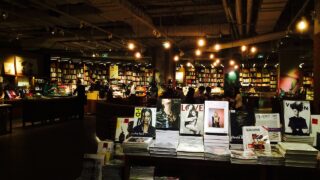本の企画を考えるとき、多くの著者や編集者は「何を伝えるか」という内容面の独自性と、「誰に届けるか」という読者層の広さの間で葛藤します。
このバランスがうまく取れているかどうかが、その企画が“売れるかどうか”を大きく左右します。
オリジナリティが強すぎると、売れない?

たとえば、ある人が「マヤ文明の死生観と現代ビジネスの関係」についての本を出そうと考えたとしましょう。
内容は極めてユニークです。
他にこんなテーマで書いている本はほとんどない。
つまりライバルがいない。
この意味では、競争優位性は非常に高いです。
しかし、そもそも「マヤ文明」に関心がある人は限られていますし、「それがビジネスにどう関係あるのか?」という接点をピンとこない読者も多い。
結果として、面白いけれど売れない本になりかねないのです。
オリジナリティは重要ですが、それが他人事になってしまっては届かない。
ニッチすぎる企画は、“興味を持つ人が極端に少ない”という致命的な弱点を抱えてしまうのです。
ターゲットを広げすぎると、埋もれる
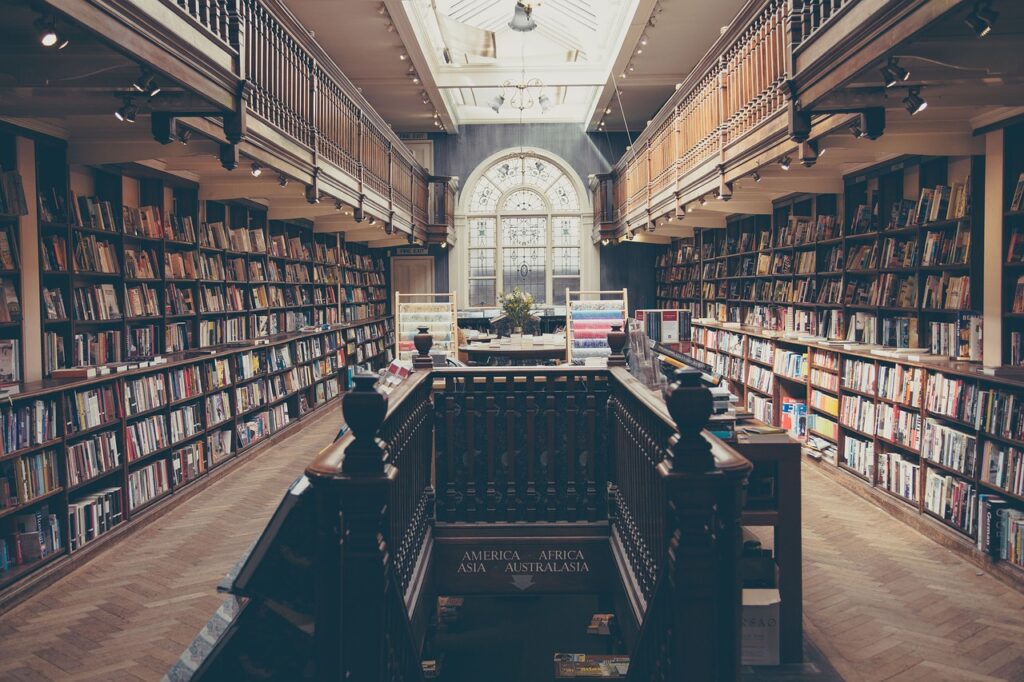
一方で、ターゲットを広げすぎた企画は、逆に個性を失います。
「人生に役立つ50の習慣」や「夢をかなえる方法」など、一見すると幅広い読者に届きそうですが、市場にはすでに同じようなタイトルが大量に並んでいます。
誰にでも届くようにした結果、誰の心にも刺さらない。
仮に売れたとしても、それは著者のネームバリューやSNSフォロワー数、あるいは広告の力によるところが大きく、企画自体の力ではありません。
売れる企画は「広くて深い接点」を持っている

では、どうすればいいのか?
答えは、ある程度のオリジナリティを保ちつつ、読者が「自分ごと」として受け取れるテーマ設定です。
たとえば、『言語化の魔力』(樺沢 紫苑)という本は、「言語化」という比較的新しい視点を取り入れながら、「自分の気持ちをうまく伝えられない」という多くの人が抱える悩みを解決するものとして企画されています。
ニッチなテーマに見えて、実は潜在的なターゲットが非常に多い。
このように、「マニアックな切り口 × 普遍的な悩み」という設計ができれば、オリジナリティとターゲットの広さはトレードオフではなく、両立する関係になり得るのです。
企画は「尖らせたうえで、間口を広げる」もの

売れる本の企画をつくるには、「尖らせる」→「広げる」というプロセスが有効です。
- まずは自分の視点や体験から生まれる尖ったテーマを考える。
- 次に、それを他人にも関係ある形に翻訳していく。
- 尖り:「趣味で始めた昆虫採集から学んだ人生の教訓」
→ 広げ:「子どもとの関わりや、自分の“好き”を貫く意味を考えるきっかけに」
この“翻訳作業”こそが、企画力の本質です。
結論:オリジナリティとターゲットのバランスを「翻訳力」で整える
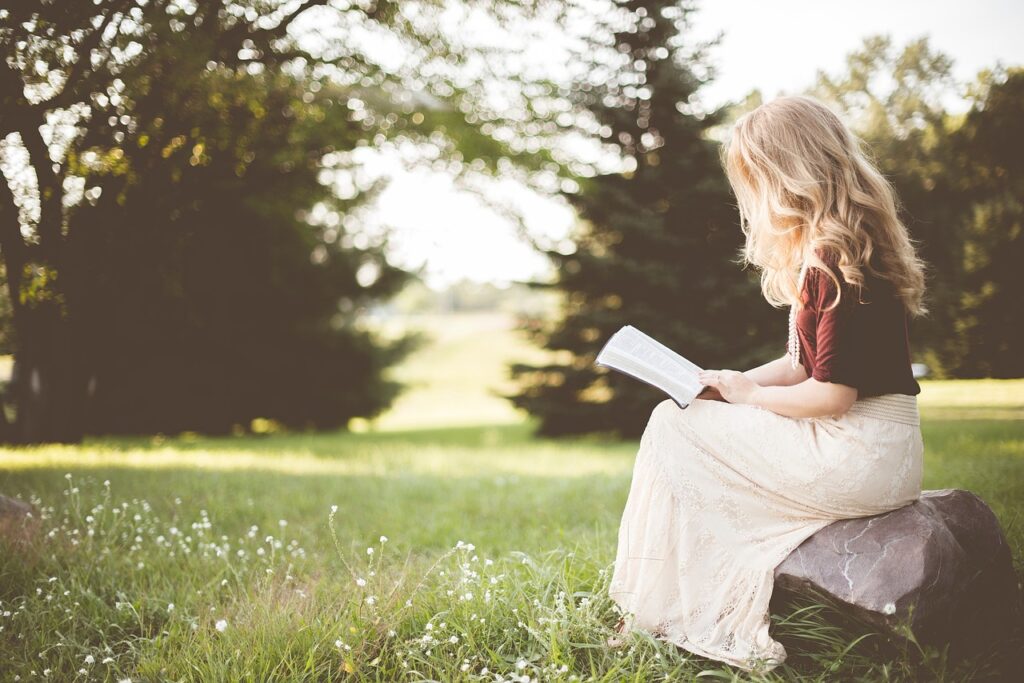
いい本の企画とは、「誰も思いつかないテーマ」ではなく、「自分にしか書けないことを、誰かにとって意味ある形に変換できる」ことです。
オリジナリティとターゲットの幅広さは、対立する要素ではありません。
橋を架けられるかどうかが、売れるか売れないかを左右する境界線なのです。