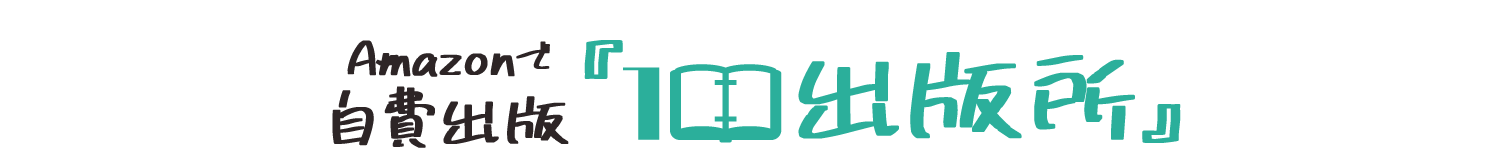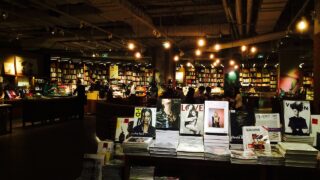書き上げた一冊の本。その完成度を左右する最後の工程が「校正・校閲」です。
「自分の目ではもう限界…でも、プロに頼むのはハードルが高い」
そんな悩みを解決するのが、今まさに注目されている「AI校正・校閲」です。この記事では、AIをあなたの優秀なパートナーとして使いこなし、本の品質を完璧に近づけるための「7つのステップ」と、どんな本にも使える汎用プロンプトを解説します。
「校正」と「校閲」の違いとは? AIで両方をカバーする

本を完璧に近づけるには、2つの異なるチェックが必要です。
- 校正:文章の「体裁」を整える作業。誤字脱字や表記の統一など、見た目をきれいにします。
- 校閲:文章の「内容」を精査する作業。事実確認や矛盾点の指摘など、内容の正しさを担保します。
この記事で紹介する7つのステップは、この「校正」と「校閲」の両方を網羅しており、AIを使ってプロレベルのチェックを目指します。
AI校正・校閲の正しい手順:鉄則は「マクロからミクロへ」

効率的に進め、手戻りを防ぐための絶対的な鉄則は、「マクロ(全体)からミクロ(細部)へ」と進むことです。
なぜなら、先に細かな誤字脱字を修正しても、後から「この章は構成が悪いから書き直そう」となれば、その修正作業はすべて無駄になってしまうからです。
まずは本の「骨格」と「信頼性」に関わる大きな問題(マクロ)からチェックし、それが固まった後に、文章の「表現」と「体裁」という細部(ミクロ)を磨き上げていきましょう。
この王道の手順で進めることで、AI校正・校閲の効果を最大化できます。
▼この順番で進めましょう
【マクロ編】本の骨格と信頼性を固める
- 【構成パターン】のチェック
- 【内容の重複】のチェック
- 【矛盾点】のチェック
- 【ファクトチェック】のチェック
【ミクロ編】文章の表現と体裁を磨く
- 【冗長表現】のチェック
- 【表記ゆれ】のチェック
- 【誤字・脱字】のチェック
【マクロ編】本の骨格と信頼性を固める

各ステップで使う「プロンプト」とは?
これから紹介する各ステップでは、AIへの指示内容をまとめた「Prompt」という枠が登場します。このAIへの「指示書」や「命令文」のことを「プロンプト」と呼びます。「何をしてほしいのか」を具体的に伝えることで、AIはその指示に沿った精度の高い回答を返してくれます。
①【構成パターン】文章の「暗黙のルール」を発見する
優れた本には、読者が無意識に心地よさを感じる「構成のパターン」があります。例えば、「章の冒頭には必ず導入文がある」などです。AIに文章全体の構造を分析させ、あなた自身が意識していない「暗黙のルール」を発見させ、そこからの逸脱がないかを確認します。
◆ Prompt
あなたは構成アナリストです。文章全体の構造を分析してください。文章内で繰り返される構成上のパターン(例えば、章の冒頭や節の終わりの形式など)があれば、それを特定してください。そして、その特定したパターンから外れている例外的な箇所があれば指摘してください。②【内容の重複】「またこの話?」を防ぐ
「この話、前にも読んだな…」読者がそう感じた瞬間、本への興味は薄れてしまいます。特に長い本では、章をまたいで同じ内容を繰り返してしまうミスが起こりがちです。AIに全体を俯瞰させ、内容の重複がないかをチェックしましょう。
◆ Prompt
あなたは構成アナリストです。原稿全体を読み、異なる章や節で、同じような内容やエピソードが重複して語られている箇所がないかチェックしてください。重複箇所が見つかった場合は、どのように修正すれば構成がスッキリするかを提案してください。③【矛盾点】つじつまの合わない箇所を洗い出す
「さっきと言っていることが違う」「登場人物の年齢がおかしい」。物語や論理の矛盾は、読者を一気に現実に引き戻し、作品への没入を妨げます。AIに客観的な視点で文章を分析させ、つじつまが合わない部分を探し出してもらいましょう。
◆ Prompt
あなたは論理分析の専門家です。文章を深く読み込み、内容における矛盾点や、つじつまが合わない箇所を探してください。矛盾している可能性のある箇所を指摘し、なぜそう考えられるのか理由も説明してください。④【ファクトチェック】情報の信頼性を担保する
特にノンフィクションや歴史を扱う作品では、事実の正確性が命です。固有名詞、年代、専門用語などの間違いは、本の信頼性を根底から覆します。AIに事実確認が必要な情報をリストアップさせ、その正しさを検証させましょう。
◆ Prompt
あなたはファクトチェッカーです。文章に含まれる、事実確認が必要だと思われる情報(固有名詞、専門用語、数値データ、歴史的記述など)を特定してください。そして、それらの情報の正確性について検証し、もし誤りの可能性がある場合は指摘してください。【ミクロ編】文章の表現と体裁を磨く

◆ ここまでで本の骨格が固まりました ◆
◆ ここからは文章の細部を磨き上げる最終工程です ◆
⑤【冗長表現】文章のキレを良くする
「〜することができる」や「まず最初に」といった表現は、文章のキレを鈍らせる「ぜい肉」です。こうした冗長な表現をAIに探し出させて削ぎ落とすことで、文章は驚くほどスッキリと、テンポ良く生まれ変わります。
◆ Prompt
あなたはプロの編集者です。文章を分析し、冗長な表現や、意味が重複している言葉(重言)を探し出してください。そして、より簡潔で分かりやすい表現への修正案を提案してください。⑥【表記ゆれ】文章の見た目を統一する
「出来る」と「できる」、「コンピューター」と「コンピュータ」。こうした表記の不統一は、読者に「雑な本だ」という印象を与えてしまいます。AIに文章全体を分析させ、統一されていない言葉(表記ゆれ)を自動で発見させることで、プロのような洗練された見た目を実現します。
◆ Prompt
あなたはプロの校正者です。文章を分析し、同じ意味でありながら表記が統一されていない単語(表記ゆれ)をすべてリストアップしてください。それぞれの表記ゆれに対して、どちらの表記に統一すべきか推奨案も提示してください。⑦【誤字・脱字】基本的なエラーを撲滅する
一つあるだけで読者の集中を妨げ、作品全体の信頼を損なう最も基本的なエラーです。どんな素晴らしい内容も、誤字一つで台無しになりかねません。AIに機械的なミスを徹底的に洗い出させ、完璧な状態に仕上げましょう。
◆ Prompt
あなたはプロの校正者です。文章を分析し、誤字・脱字、明らかな日本語の間違いをすべて指摘してください。AI校正・校閲を成功させるための3つの心得

1. 一度に全部頼まない(タスクと文章量を分割する)
AIに仕事を頼む上で、これが最も重要な心得です。面倒に感じても、必ず「1ステップずつ(タスクを1つに絞り)」「文章を区切って(適切な分量で)」依頼してください。なぜなら、AIには一度に処理できる情報量やタスクに限界があり、それを超えると精度が著しく低下してしまうからです。
2. AIを鵜呑みにしない
AIは文脈やあなたの意図を100%理解するわけではありません。提案はあくまで「指摘」と捉え、採用するかどうかの最終判断は、必ず著者であるあなた自身が行ってください。
3. 情報漏洩に注意する
未公開の原稿はあなたの重要な知的財産です。使用するAIサービスの利用規約を確認し、入力データが学習に使われない設定(オプトアウト)ができるかなどを確認しましょう。
最後に

AIは、あなたの執筆作業を劇的に効率化してくれる強力なパートナーです。しかし、最後のクオリティを決めるのは、あなたの作品への愛情と、読者に届けたいという想いです。
この7つのステップでAIを使いこなし、自信を持ってあなたの本を世に送り出してください。
素晴らしい一冊が完成するのを、心から応援しています!